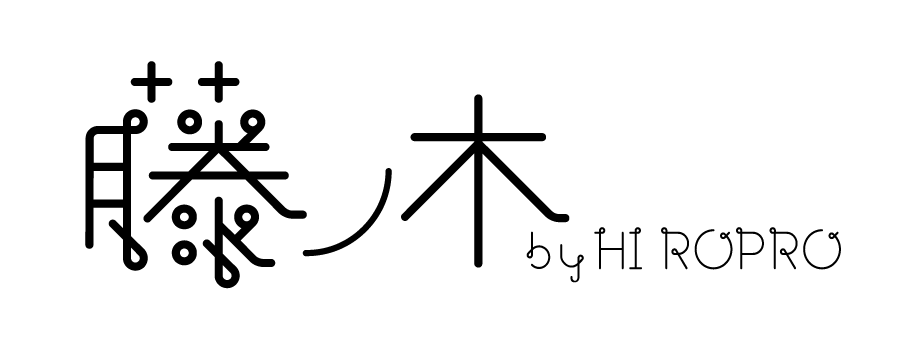1.
昔、ガンジス河のほとりに一匹の山犬が住んでいた。ある日、彼は獲物を探して歩き回っているうちに、大きな体を横たえて寝そべっている一頭の象にぶつかった。山犬は慌てて森に逃げ込み、しばらくの間遠くから様子をうかがった。
ところが象は身動きひとつしない。眠っているにしても、時たま大きな耳を揺り動かすはずの象が、微動だにしないのだ。
「もしかしたら死んでいるんじゃないか。」
山犬は恐る恐る象に近づいていった。しだいに大胆になり、ついに象の顔を真近に見られる所まで近づいて前足でつついてみた。ところが、象はやはり動かない。山犬は象が間違いなく死んでいることを知り、踊り上がって喜んだ。
「やっと獲物にありつけたぞ。しかもとびきり大きな象ときている。これは大したごちそうだ」
そう言いながら、すぐさま象の長い鼻にかみついた。
「ひゃあ、硬い。なんていう硬さだ、これは」
まるで鋤(すき)をかむようで歯が立たない。そこで白い牙にかじりついてみたが、柔らかいはずもない。今度は耳をかんだ。
「ひえっ」
さらさらしていて、まるでざるの端をかむようだった。次には腹をかもうとしたが、それは米を蓄える大きなつぼのようで、まるで歯が立たない。足をかじってみた。全く石うすだとしか思えない。細いしっぽをかじってみてもきねのように硬かった。
「えいっ、どこをかじったらいいんだ。大きいばかりで、かじりつくところがないじゃないか」
いよいよいら立ってきた山犬は、めちゃくちゃに象の周りを走り回ってはあちらこちらにかじりついた。最後に、山犬は象の肛門にかじりついた。肛門は象の体の中で唯一柔らかな所だったのである。しかもおいしかった。山犬は舌鼓を打って肛門を食べた。食べているうちに、山犬の体は肛門をくぐって象の体の中にすっぽりと入り込んでしまったのである。
腹の中に入ると、山犬は象の腎臓や肺を食べだした。それぞれ味が異なっており、山犬は夢中になって食べ続けた。のどが渇くと象の血を飲み、疲れるとそのまま体を横たえた。大きな象の腹の中は、柔らかな草の茂みに横たわっているように心地良かった。
すっかり満足した山犬は、膨れた腹をたたきながら歌うように言った。
「象の腹ってなんてすばらしいんだろう。ごちそうは無尽蔵だし、雨が降ろうが風が吹こうがへいちゃらだ。おれにはもってこいの家ができたってわけだ」
こうして山犬は象の腹の中を一生の住みかと決め込み、その中でのんびりと暮らし始めたのである。
2.
それからしばらくたったある日のこと、いつものようにごちそうを腹いっぱいに詰め込んで昼寝をしていた山犬は、ふと目を覚まし辺りが暗いのに気づいた。もともと薄暗かったのだが、確かに昨日よりも暗くなっている。
「暗いなぁ、どうしたんだろう」
実は、象の死体が連日の日照りでからからに乾いて縮み始めたのである。今までは山犬が潜り込んできた肛門から外の光が射し込んでいて、不自由しないほどの明るさであったのだ。ところが、象の死体が干上がり始めたために、肛門の穴も日一日と小さくなっていったのである。
明くる日、山犬の住みかはついに真っ暗になってしまった。肛門の穴が、ぴたりとふさがってしまったのである。山犬は慌てふためいた。脱出しようにも真っ暗で肛門がどこにあるのか分からない。出口を失った山犬は象の腹の中であちらに突き当たり、こちらにぶつかって跳ね回った。それはちょうど釜の中で煮え立つ米粒のようであった。のどはからからになり、疲れきった山犬はとうとうその場に倒れ込んでしまった。
その夜、久しぶりに大雨になった。激しい雨は、からからに干からびた象の死体を一晩中たたき続けた。朝になって雨は止んだ。水気を吸って膨らんだ象の腹の中は、うっすらと明るかった。肛門が開いて、そこから小さな星のような光が射していたのである。
「しめた」
山犬は立ち上がり、その光めがけて突進した。そして外へ飛び出すことができたのである。それでも山犬は恐怖の念から逃れることができず、まぶしい太陽の下をがむしゃらに駆け続けた。小さな肛門の穴を突き抜けたので山犬の体の毛はすっかりすり切れ、木の肌のように赤くつるりとしていた。
そんなことを気遣う余裕もなく走り続けた山犬は、とうとう力尽きて倒れてしまった。山犬はその場に横たわり、目を閉じた。
「ああ、ひどい目に遭った」
山犬は自分の愚かさを思い知った。誰のせいでもなく、ただ自分が貪欲で卑しかったためにこんな苦しみを味わう羽目になったのである。恥ずかしさが山犬の体中を駆け巡り、顔が火のようにほてった。
それ以後、山犬は象の死体に出くわしても見向きもせずに通り過ぎるようになったという。
(ジャータカ一四八)