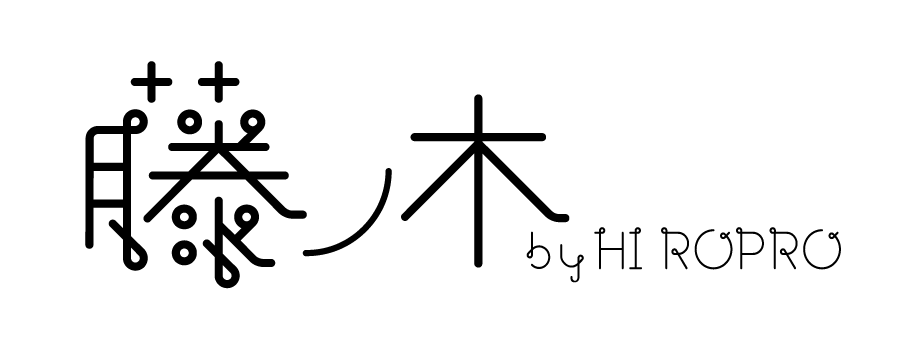百獣の王
昔、ブラフマダッタ王がバーラーナーの都で国を治めていたころのことである。
都のはるかかなたには、万年雪に輝くヒマラヤの山々がそびえていた。
下方の岩山に一つの大きなほら穴があり、そこには金色のたてがみをもつ威風堂々としたライオンが住んでいた。

ある朝のことだった。
百獣の王ライオンは、ほら穴からゆう然と身を起こした。
金色のたてがみを朝日に輝かせながら四方をながめ渡し、一声高くうなり声を上げると、獲物を探しに森へ向かった。
巨大な木々がこんもりと茂っているその陰で、水牛が朝の清らかな空気を吸っているのを見つけた。
ライオンはあっという間に水牛ののどぶえをかみ切った。
ライオンの朝食は、丸々と太った水牛だった。
水牛の肩の肉だけを食べると、ライオンはもう満腹だった。
「残りは森の獣たちに残しておこう」
腹ごしらえのできたライオンは、森の中ほどにある美しい湖のほとりに下りると、湖面に映った雄々しい自分の姿をながめながら、十分に水を飲んだ。
家来になった山犬
その帰り道、ばったりと山犬に出会った。
前の日からなにも食べていなかった山犬は、えさを探すのに夢中だった。
思いがけずライオンに出会った時には、もう逃げ隠れできなかった。
とたんに、山犬は知恵を働かせた。さっとライオンの足元にひれ伏したのである。

百獣の王さま、おはようございます。
ごきげんはいかがでございますか
満腹のライオンは上きげんだった。



おう、おはよう
朝の散歩かね
山犬は命がけだった。
震えを隠しながら、やっとのことで声を出した。



わたしは、王さまをお慕い申し上げている者でございます。
どうか、あなたさまの家来にしていただけないでしょうか



よかろう、わしについてまいれ。
お前にうまい肉を食わせてやろう



ありがとうございます
山犬は今まで、ライオンの家来になろうなどとは夢にも思ったことがなかった。
しかし、とっさの知恵で家来になることができた。
そして、その日から腹をすかせてうろうろすることもなくなった。
ライオンの食べ残しをたらふく食べることができたからである。
山犬は数日後にはめきめき太り、毛並みも見違えるほどりっぱになった。
ライオンは山犬に命じた。



お前は体が軽くてすばしっこい。
森の中で遊んでいる象や馬、牛やシカなど、お前が食べたいと思う獲物を探してくるんだ



はい



獲物を見つけたら、すぐにもどってきてわしに報告し、こう言うんだ。
『百獣の王さま、なにとぞあなたさまのご威光をお示しください』とな。
分かったか



分かりました
山犬は足が早い。
森中を駆け回って獲物を探してきては、ライオンに敬礼して言うのだった。



王さまのご威光をお示しください
するとライオンは稲妻のように飛び出し、その獲物を引っ捕らえるというわけだった。
山犬は幸福な日々を送った。
森の中で空腹を抱えながらえさを探し回っていたことが、まるでうそのようだった。
毎日残り物ではあるが、おいしいごちそうをたらふく食べることができたのだった。
呪文に違いない
ところがしばらくして、山犬には身の程知らずな欲の芽が育っていった。
ライオンが獲物を捕まえるとまずおいしい部分を食べ、山犬はその後で残り物を食べるというのがしゃくにさわり始めたのだ。



おれがまずあちこちを駆け回って獲物を探し出し、それをライオンに報告する。
するとライオンは飛んでいってそれを捕まえるのだ。
共同作業じゃないか。
それなのに、ライオンだけが先においしい所を食べてしまうのはおかしいじゃないか。
ライオンも四つ足だし、目は二つ、耳も二つ、口は一つ。
この山犬さまと、どこが違うというのだ。
毎日残り物とはいえ象や馬などの上等の肉を、しかもたらふく食べているうちに、山犬にはどんどん高慢な心が生まれだしたのである。



ライオンがおいしい所を食べるのは、自分で獲物をかみ殺すからだ。
もし、おれがをかみ殺したら、ライオンに遠慮なんかしなくていい。
さっさとおいしい所が食べられる……
そうだ、あのライオンが象やら馬をかみ殺せるのは、このおれさまが敬礼して『王さま、ご威光をお示しください』と言うからだ。
これは、ひょっとして魔法の言葉じゃないだろうか。
そうだ、呪文に違いない。
この呪文を唱えてやるから、ライオンは稲妻のように駆けていって象をかみ殺すほどの力が出せるのに違いない。
きっとそうだ。
この呪文がすばらしい怪力をわき上がらせるからだ。
山犬はさらに思いついた。



だれかがおれにこの呪文を唱えてくれれば、おれはライオンのような怪力をもつことができるだろう……
なんといってもライオンは強い。
百獣の王に唱えてもらえば、最高の威力を発揮できるに違いない。
そこで山犬は、ライオンの前にひざまずいた。



王さま、お願いがございます



なんだね



わたしは今まで、あなたさまが殺した象の肉をいただいてまいりましたが、一度だけ、自分で象を殺してその肉を食べてみたいのです。
あなたがお座りになっているほら穴に、わたしを座らせてください。
そして、わたしの前で敬礼して『山犬のご威光をお示しください』と呪文を唱えてください。
どうか、一生のお願いです。
ライオンは山犬の大それた願いにまるで取り合わなかった。
けれど、山犬はしつこかった。
明くる日も、その明くる日も、頭を地面にすりつけてライオンに嘆願した。



お前に象をかみ殺せるはずがない



いいえ、きっとかみ殺せると思います
ライオンは鼻で笑うばかりだったが、山犬の嘆願は続いた。
4.
それから幾日かが過ぎた。
森の中のマンゴーの木の下を、元気そうな若い象がのっしのっしと歩いていた。
ライオンはそれを見つけると、ふんふんとうなずきながら山犬を呼んだ。



おいしそうなのがいるぞ。やってみるか



は、はい。王さま、早く呪文を



よし
ライオンは山犬をほら穴に座らせて敬礼し、呪文を唱えた。



山犬のご威光をお示しください
山犬は、ばっと地面をけって象に向かって突進した。そして象の額に飛びついた……



ひえい
山大の悲鳴が響いた。
山犬は象の足元に振り落とされ、右足で踏みつぶされていた。
頭蓋骨はみじんに砕かれた。
象はばらばらになった山犬の死体を足でかき集め、その上に大小便を引っかけて一声高く鳴き叫んだ。
そして、森の奥へ姿を消した。
ジャータカ143
『仏教説話大系』第6巻
「哀れな山犬」より