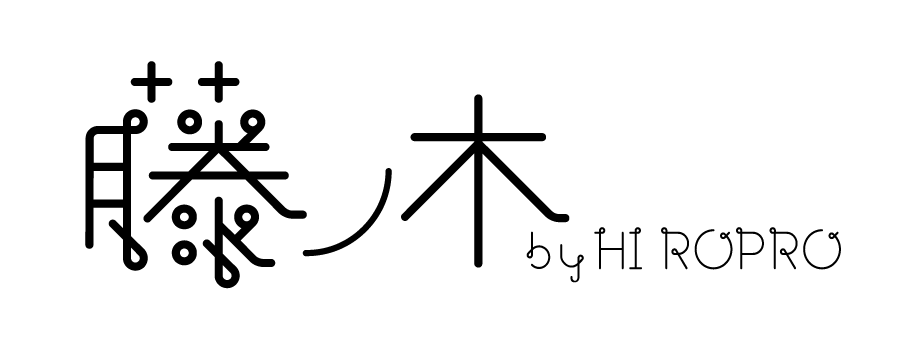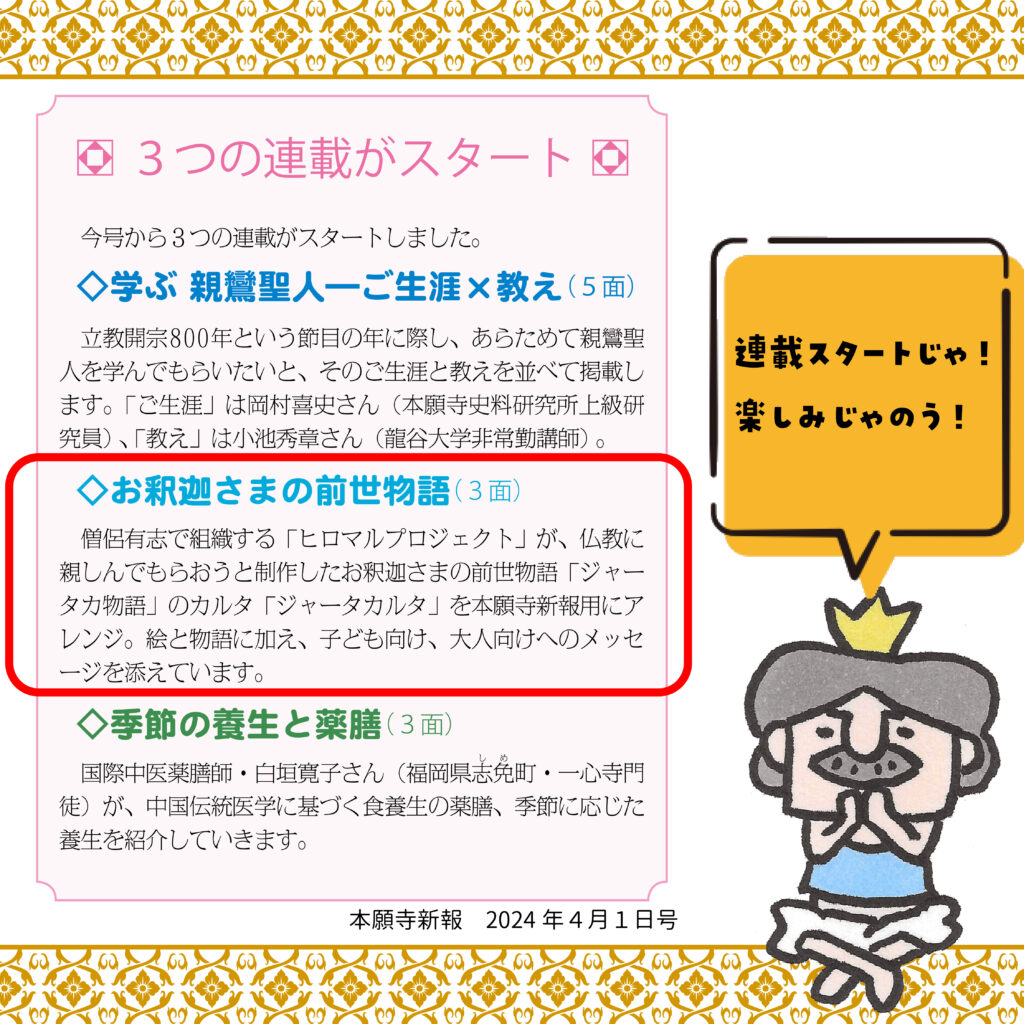ヒマラヤから流れ出るガンジス河が大きく弧を描いて流れていた。その岸一帯に、ウドゥンバラの森があった。夏になると、ウドゥンバラの赤い実が枝一面にたわわになって、遠くからは、森一帯が赤らんで見えた。
その森に、数千羽のオウムが住んでいた。オウムの王は、まだ若かったが無欲な鳥だった。ウドゥンバラの実が熟れる時も、必要なだけ食べて、それ以上は食べなかった。
実がなくなってからは木を枯らさない程度に木の芽や葉をついばみ、ガンジス河の水を飲んで満足し、決してほかの土地へ移ろうとはしなかった。この様子を見て、天界の神、帝釈天は感心した。
たいていの鳥は、食べ物がなくなる季節になると、食べ物を求めて他の土地に移動していってしまうのに、なんという無欲な鳥たちだろう。
そこで、帝釈天はオウムの王を試そうと思い、神通力によって、ウドゥンバラの木をすっかり枯らしてしまった。そのため、枝は落ち、幹は吹きさらされて穴だらけになり、地面は木のくず粉で埋もれてしまった。
だが、オウムのたちはそれでもその森を動かなかった。彼らは木のくず粉を食べ、ガンジス河の水で飢えをしのいだ。帝釈天はそれを見ると、白鳥に姿を変えてウドゥンバラの森に降り立った。そして、オウムの王を見つけると、話しかけた。

果実がたわわに実る時、鳥たちは群れを組んでやって来て、その実を食べる。しかし、木が枯れて果実がなくなってしまえば、そこを飛び去ってしまう。寒さに強い我々でさえ、いてつく冬にはこの川辺を去る。鳥とはそういうものだ。
それなのに、お前さんたちはどうして去らないのだ。そのわけを教えてくれないか。



それはこの木に対する感謝の気持ちからだ。
わたしたちは、今日までこの木によって命を永らえてきた。ある時は実や葉を食べ、ある時は枝に休み、この木と語りながら日々を過ごしてきた。この木はわたしたちの友人であり、血を分け合った仲間といえよう。
本当の友達は、生死、苦楽をともにするものだ。木が枯れてしまったからといって、どうしてこの森を捨てていかれよう。
白鳥は、オウムの王の言葉に感動して言った。



なんという深い友情だろう。私は今、友情というもののすばらしさをしみじみと教えてもらった。ありがとう。
このお礼に、なにか贈り物をさせてもらおう。なんなりと言ってほしい。



もし、わたしたちに贈り物をくださるのなら、この木を再び生き返られてほしい。それ以外のものは、なにもいらない。



ああ、いいとも、木を生き返らせてみせよう。
白鳥はそう言ったかと思うと、帝釈天の姿にもどって、ガンジス河からくんできた水をウドゥンバラの木々に注いだ。すると、不思議なことに枯れ木はみるみる生気を取りもどして、たちまち枝が生え、葉が茂って、赤い果実が枝いっぱいに実った。
これを見たオウムの王は、目を輝かせて言った。



ありがとう、本当にありがとう。これでわたしたちの森がもどった。
オウムたちの喜ぶ様子に、帝釈天はしみじみとつぶやいた。
生き物は、皆このようでありたいものだ
そして、そのまま天に帰っていった。
ジャータカ429
『仏教説話大系』第5巻 「オウムの森」より