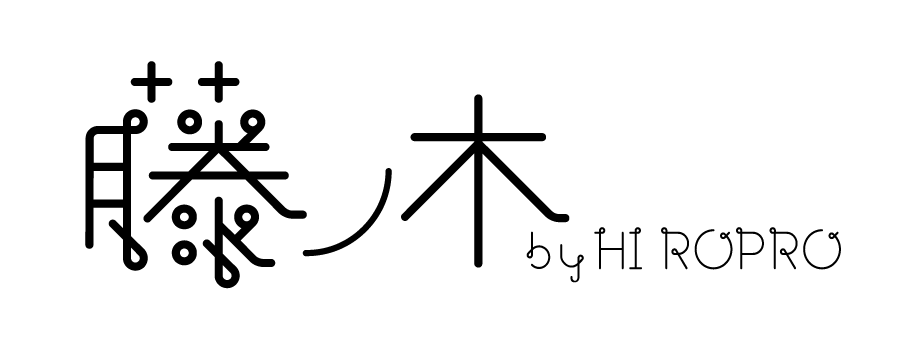カラスの悪知恵
昔、バーラーナシーの都では、みんなが鳥をかわいがって暮らしていた。
自分で飼っている鳥はもちろんのこと、野鳥もかわいがった。
それぞれの家では、鳥が暮らしやすい所にかごをかけておいて、自由に出入りできるようにしてあった。
おかげで鳥たちは、夜になっても屋根の下で安らかに眠ることができた。
ある金持ちの家で料理人として働いている男も、自分の台所に鳥かごを一つ下げていた。
そこには白いハトが住みついていて、夜明けにかごを飛び出しては食べ物を探しにいき、日暮れになると帰ってきた。
ある日のこと、一羽のカラスが飛んできた。

なにか、いいにおいがするぞ
そっと台所の中をのぞいてみると、大好きな肉や魚が山ほどある。
カラスはしばらくその辺りをグルグル飛び回ってにおいをかいでいたが、そのうち、たまらなくなり、なんとか台所に潜り込んで、肉や魚を食いたいものだと考えた。
カラスはその家の鳥かごにハトが住みついているのを見ると、ある計画を思いついた。
次の日の夜明けに、ハトが飛び立つとカラスはその後にぴったりとついていった。
ハトが空高く舞えばカラスも舞い、ハトが風に乗って翼を広げればカラスも広げた。



いったい、どういうつもりでそう後をつけてくるんだい
ハトはカラスに尋ねた。



いや、すみません。でも変に思わないでくださいよ。
ぼくはあなたの飛び方がすっかり気に入ってしまったのです。
一緒に飛んでいると、とても気持ちがいいもんですからつい、ついてきてしまいました。
カラスは答えた。
ハトはなんとなくおかしいぞと思ったが、カラスが別に悪いことをしたというわけでもないし、そのままにしておくことにした。



カラスのことだから、きっとすぐに飽きてしまうだろう
ハトはあまり気にしないことにした。
けれども、カラスはいつまでたってもついてきて、ハトのまねばかりしていた。
そして、とうとう牧場の近くまでついてきてしまった。



カラスよ、君の食べ物はぼくらハトとは全然違う。
ここにはぼくらの食べる草の種なんかはたくさんあるけれど、君の好物はありませんよ



なあに、構いませんよ
カラスはそう言って、ハトについてきた。



おれの好物はもっと別なところにあるのさ
カラスは危うく口をすべらせそうになったが、息を飲み込んでごまかした。
思い通りにいかないカラス
牧場に降りると、ハトは草の実などを食べた。
しかしカラスは、牛のふんをのけてやっと昆虫を少し見つけたりして、なんとかおなかを満たした。
夕方近くなって、ハトが料理人の台所めざして飛び立つと、カラスはまたそれについていき、とうとう料理人の家の中まで入ってきた。



おやおや、うちのハトが友達を連れてきたよ
それにしても、ハトとカラスの友達というのは、ちょっと変だな
料理人はそう言って、もう一つのかごを台所に下げてくれた。
カラスはそこでスヤスヤ眠った。
次の日の朝早く目覚めると、ハトがまた飛んでいこうと言うので、カラスは仕方なく後についていった。
行く途中、料理人の家へ、たくさんの肉や魚が運ばれていくのが見えた。
カラスはそれを空の上から、よだれをたらしながらながめていた。
その日一日、カラスは肉や魚のことばかりが頭に浮かんで、ずっとぼんやりしていた。
ハトのまねをして飛ぶのもいい加減いやになってきて、早く帰ろうと何度もハトにせついた。
家にもどると、肉や魚はみんな料理されて金持ちの家へ運ばれて、なにも残っていなかった。



ちえっ
カラスは舌打ちした。



また明日になれば、肉や魚がいっぱい運び込まれてくるに違いない。
明日はなんとか家に残って、そいつを失敬してやろう。
カラスは知恵を絞って考えた。
カラスの嘘
翌朝、ハトはいつものように早く目を覚ますとカラスを誘った。
けれどカラスは、隣のかごの中でわざとじっとしていた。



どうしたんだい
ハトが尋ねた。



いや、どうも体の具合が悪い
カラスは腹を押さえながら答えた。



そうかな。
君の羽の色つやは悪くないよ。
ハトがカラスをのぞき込んで言った。



それが、なんかおなかが痛いんだ



そうも見えないが……



いや、寒気もする



そりゃ、いけないな



うん、頭も痛いし、足もだるい
カラスはありったけのうそを並べたてた。
ハトはどうも怪しいと思いながらカラスの様子を見ていた。
カラスは、時々震えてみせたりしながら、ちらっとハトの様子をうかがっていた。



とにかく、翼が重くって、飛ぶのがつらいんだよ。
外に出たらせきも出てきそうだ



そうか。
では病気だというものを無理に連れていくことはできないな。
けれどひょっとして君、この家のものをねらっているのではないだろうな



とんでもない
カラスは首を振った。



まあいい。
人間の食べ物は鳥には合わないから、変な欲は持たないほうがいい。
ひどい目に遭うのは自分だからね。
本当に病気なら、じっとお休み。
ハトはそう言うと、飛び立っていった。
報いを受けるカラス
カラスはうまくいったぞと思いながらかごの中で待っていた。
思ったとおり、この日もたくさんの肉と魚が運び込まれてきた。
カラスは、もううれしくてたまらなくなった。
料理人は早速、肉や魚を切ったりひいたりして準備に取りかかった。
それぞれをなべやさらに入れてから、料理人は台所を出ていった。



しめた
カラスはのそのそとかごから出てきた。
そして様子をうかがって、料理人が帰ってきそうにないのを見ると、台所のなべやさらの間を歩き回った。
そうして品定めをしていると、なにか自分が大金持ちになったようで胸がわくわくした。



ははは……なんでも取り放題だ
ふむ、ひき肉では腹が膨れないな、こっちのこま切れのほうにばくつくか
カラスは気取ってそう言うと、こま切れ肉の入っているなべの所に止まった。
ふたが少しずれているので、そこにロばしを突っ込んで中の肉に食いついた。
ところが、欲張って大きな肉をつかんだので、取り出す時にふたに引っかかり、ふたが床の上に落ちても のすごい音を立てた。
音を聞きつけた料理人が、慌てて部屋に入ってきた。
ちょうどカラスが大きな肉を飲み込もうとして、目を白黒させているところだった。



この、どろぼうガラスめ
料理人はカラスの首根っこを捕まえた。
そして、あっという間に羽をむしって丸裸にしてしまうと、からしにぴりぴりとする調味料をたくさん混ぜて、カラスの体にすりつけた。



丸焼きにして食っちまわないだけありがたいと思え
料理人はカラスをかごの中に投げ入れた。
夕方になって帰ってきたハトは、かごの中で苦しんでいるカラスを見つけた。



わたしの言ったとおりになったではないか。
忠告を聞かなかった罰だ。
欲張った報いは必ず自分に返ってくるのだよ。
しかしこのわたしも、こんなどろぼうを家に入れたのではもうこの家にとどまっているわけにもいかない。
ハトは、料理人の家を去っていった。
カラスは毛をむしられ、かごの中で丸裸で苦しみ、のたうち回って死んでしまった。
ジャータカ42
『仏教説話大系』第5巻
「ハトとカラス」より